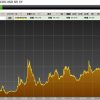Warning: Undefined variable $nlink in /home/metheny68k/47ossan.com/public_html/wp-content/themes/ystandard-child/functions.php on line 65
Warning: Undefined variable $nlink in /home/metheny68k/47ossan.com/public_html/wp-content/themes/ystandard-child/functions.php on line 65

ヤンゴン、ミャンマー(2005)
(前回からのつづき)
両替がしたかったが、あいにくレートのいい市場内の店は今日も明日も休みだった。ホテルはレートが悪く、他の両替所を探す必要がある。
ミャンマーに入国するとき、旅行者は空港で強制的に一定額のドルをFECという外貨兌換券に両替させられる。ところが市中では普通に使えないので、さらにチャットという通貨へ両替せねばならない。それは否が応でもこの国に金を落とさせるための馬鹿げた制度で、公定レートは一ドル=一FECだが、実勢レートではドルの方が価値が高かった。
ヘンネリは、商売をしている友人がやっている店――といっても両替専門店ではなく、タイや中国から現物を買うときに必要なドル現金やFECを用意するための闇両替――と、公認の両替免許を持つ雑貨屋に案内してくれた。どっちを選ぼうと好きにすればいいと彼は言った。バスのチケットを買う場合も、手数料を取るホテルより代理店で買ったほうが安く、必要ならそこまで案内してくれるという。
あちこちを彼と歩きながら、猜疑心が湧き起こっていた。なぜ彼はこんなに親切にしてくれるのだろう。たとえばぼくを両替所に案内することで、仲介料の類の利を得ようとしているのだろうか。それならそれでよかった。親切を装って見返りを期待されるくらいなら、はっきりとそう言ってくれたほうがいい。ただ、彼の口ぶりからすると何の益もなさそうなのだ。それでぼくは考えていた。もしほんとうに善意だけでやってくれているのなら、こうして疑念を膨らませている自分は何なんだ……。
「どうしてビジネスをしたいの?」とぼくは言った。「なんでそんなにしたいのか……」
小さな茶屋で低い椅子に腰掛け、ぼくたちは甘い紅茶を飲んでいた。
「ぼくには三つの哲学があるんだ」と彼は言った。
ひとつは、部屋を買うこと。ふたつ目は、貧乏な人達に与えること。最後は、寺に寄進すること。目標といった方が適当だろうそれらを彼は哲学と表現した。部屋は、友人達が自由に寝泊まりでき遊びにも来れるようにしたい。
「困ったときはぼくも友人たちに助けてもらうし、彼らはお金をくれる。それはお互い様だからね。やれる人間がやればいい。ぼくは家族の面倒を見なくてもいいし、自分の好きなように生きられる。ラジャは家族があるからそういうことはできない。ヤツは少しやさしすぎるしね」
深い動機は不明だが、彼が強くそれらを望んでいることはわかった。単に自分のことだけを考えているのでもなさそうだ。
「でも、金はあとからついてくる」彼はつづけた。「やることをやりさえすればね。大切なのは、成功するためにはまず投資して、返ってきたものをまた投資することだよ。ビジネスだってなんだって一緒さ。人に親切にすれば、それは倍になって返ってくる」
「親切?」ぼくは言葉をはさんだ。「何かを返してほしくて親切にするの?」
彼はうなずいた。
不思議なことに、彼はそうした話を友人たちと共有していないらしかった。理由を訊ねると、別の意味にとったのか彼は少し表情を硬くして答えた。
「ビルマ族とはアイデアを共有しない。彼らは物事をいい方向に考えないから」
他にも一度彼が感情的になったことがあった。もし投資者を募るとすればその結果の取り分はどうするのかとぼくが何気なく訊ねたときだった。
「リスクを冒すのはぼくなんだから、ぼくがいちばん取るのは当然だ」ヘンネリは少し憤然として答えた。「空港から監獄行きになるかもしれないのはぼくなんだ」
投資者が彼を信頼するのは当然の前提で、彼が金を持ち逃げしたり失敗する可能性があるという投資者側のリスクは考えていない。
今はまだ資金がないから他人とアイデアを共有しなければならない。チケット代や、軌道に乗ればまとまった質のいい宝石を手に入れる金が必要になる。しかし、じょじょに自分の出資額を増やしていくつもりだと彼は言った。それでも、彼はぼくに金を出してほしいという素振りは見せなかった。

ヤンゴン、ミャンマー(2005)
同宿の日本人二人とヘンネリと四人で夕食をとり、二人に両替の話をした。明日もボージョー市場は休みで、ホテルよりも今日の店の方がレートがいい。もちろんかいつまんで宝石の話もし、好きに判断するよう言った。必要なら両替すればいいし、したくなければそれでいい。彼らは、ヘンネリが宝石ビジネスをしようとしていると聞いて警戒したようだった。
おごるから何か食べればとうながしても、ヘンネリはビールしか飲まなかった。食事は友人の家に帰ってから皆でとるのだという。ライトを浴びて金色に照り輝くスーレーパゴダの前を歩きながら、彼は得意げに言った。
「ぼくは精神を鍛えてるから、ちょっとしか食べなくても大丈夫なんだ。毎朝、瞑想をしてるからね」
「瞑想?」
「そう。高僧になると、空に浮かぶこともできる」
「……」
彼の無邪気な目に、パゴダの光が映っている。
「いつかは、精神集中でろうそくの火を消してみせるよ」
「できそうなの?」
「一ヶ月前にはじめたところだからまだだよ」彼は笑った。「でも努力すればぜったいにできるようになるさ」
彼の思考には成功へのステップが強く組み立てられているようだ。しかし、努力すれば超自然現象的能力さえ獲得できるという考え方には違和感を抱かずにはおれなかった。
翌日、茶屋で待ち合わせした。ぼくともうひとりの日本人が待っていると彼がやってきて、両替レートの確認に電話をかけに行った。戻ってきた彼は、金の価格が下がっているので、レートは昨日よりも少し低いのだと言った。紅茶代を払おうとすると、彼がすでにぼくたちの分を払っていた。ぼくたちが礼を言うと、「三ヵ所への電話代に六十チャットも払ったよ」とヘンネリはさりげなくつけくわえた。彼の案内で両替を済ませると、
もうひとりの日本人が言った。
「お礼したほうがいいんですかねえ」
「気持ちでいいんじゃないんですかね」
ぼくは食事でもおごるつもりだった。結局もうひとりの日本人は二百チャットのラッキーストライクを一箱ヘンネリに渡した。
ぼくのバスチケットを買いにヘンネリと代理店までかなりの距離を歩いた。この方が安くすむと彼は得意げだけれど、歩く労力と謝礼を考えればホテルで手に入れたほうがよほど安あがりだ。ただ、彼が好意でしてくれるなら金は優先事項ではなかった。
午後、ぼくがホテルの人気(ひとけ)のないフリースペースに座っていると、取り乱した様子で日本人の女の子がやってきた。探している旅行者がいるらしい。彼女はぼくの横に座るとぺらぺらと話しだした。今は外大生でミャンマー語を勉強しており、日本での就職前にここでしばらく働くことになり、やってきたところなのだという。昨日、用事があって出かけたとき、バスの乗り継ぎに間違い、わけのわからない場所に行ってしまった。どうやって帰ればいいのかと途方にくれていると、通りがかりのお坊さんが同方向に行くらしく、一緒にタクシーに乗ってついてきてくれた。もちろんそこまでの費用は彼女が持ったが、彼は、自分の住居までのタクシー代まで要求してきたのだという。
「どうしてわたしが彼の分まで払わなくちゃいけないのって思って」彼女は憤っていた。「お坊さんだから信用してたのに。私に親切だったのはただタダ乗りしたいだけだったのかって」
それから彼女はミャンマー人が信用できなくなり、何か親切にしてくれようとしても、下心があるのではと疑心暗鬼になって逃げているらしかった。
「今は来たことをちょっと後悔してて……」
そして、とにかくすべてが不安なのだと彼女は言った。前回に来た時は旅行者だったこともあり、人はとても親切で――実際にそうだったのかもしれないが――なんていい国なのだろうという感想を抱いたが、やはり住んでみるといろいろ印象も違う。トイレ一つにしても、職場の人に用意してもらった住居は清潔だがトイレが洋式ではないので、自分で金を出して別のところに移ろうかとさえ――今はまだホテルに泊まっているが――考えている。
そこまで一気にしゃべると、彼女は憂鬱そうな表情のまま沈黙した。彼女の口から言葉が出てこなさそうなのを見て、ぼくは訊いた。
「アウンサンスーチーさんって今どこにいるんですかね」
ミャンマー語を勉強しているくらいだからこの国の情勢にも通じているのではないかと思ったが、彼女は固い口調で言った。
「さあ、知らないです。わたしはそんなことはまったく興味はないし、興味なんて持たない方がいいから……危険だから」
(つづく)

ヤンゴン、ミャンマー(2005)
(注)この紀行は1999年のもので人名は仮名です。文中の登場人物と写真とは関係がありません
◎関連エントリ