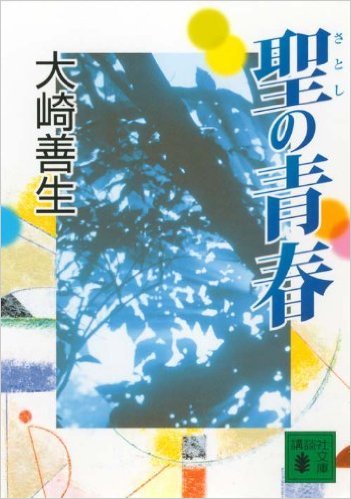なぜこれまで機会がなかったのかとは思うけれど、前から気になっていた本書聖の青春 (講談社文庫)を先日やっと一気に通読した。作者はさぞ精魂傾けて書いたのだろうと伝わってきて、感じるものの多い、いい本だった。
29歳で早逝した、村山聖(さとし)棋士を描いたノンフィクションだ。5歳のときに腎ネフローゼを患い、一年の半分以上を病院のベッドで送るなかで、将棋に巡りあい、そこからA級棋士となる日々が描かれている。
その人物像が活き活きと伝わってくる、魅力的なエピソードが満載なのだが、そのサイドストーリーとして、親としての子供への接し方について考えさせられるものがあった。
村山聖は、幼い頃から数え切れないほど入退院を繰り返し行動を制限されたために、期せずして型破りな教育を受けることとなる。そこには、必死で道をさぐった親の、できる限りのものを与えてやろうという決心や献身的なサポートがあった。限定された自由のなかで精一杯自由をサポートすることによって、子供の能力がいかに伸びるか。その一例であるように感じられた。
もちろん単純な方法論で同じ結果が得られるはずもない。ただ、子供にとって、やりたいことをなんでもできる環境が理想的とされるけれど、もしかしたら、その恵まれた状況ゆえ、かえって広大な道に迷うことも多いのかもしれない。なんでもできる。だから目移りする。さらに、減点法で評価される日本社会では、劣った点を突っ込まれ、穴を埋めるべく励まされる。やがて他律のパターンにはまり、自らの意思を見失ってしまうのだ。
高度成長期に生まれ育った日本の子供の多くは、多少の貧富の差はあろうとも、義務教育のなかで恵まれた教育を受けてきた。教育機会の平等は、選択の自由をもたらす。一時的であろうと、錯覚であろうと、選択肢が無限にひろがっているように感じられる実感を持ちうる時間は、海外で貧困のなかで選択肢のない子どもたちの生活と比すると、いかに恵まれたことか。
村山聖は、そこから外れざるをえない状況のなかで、もがいてきた。不自由さを強く意識するからこそ、そこに自律の意思が生まれた。病気下の条件と将棋という世界のなかで、ピタっと自律のベクトルが重なっていく。
彼が出会う人々の描写も魅力的だ。とくに師匠の森信雄六段との生活と愛情あふれたやりとりに心を打たれた。
ある日、森氏と酒を飲んだ著者が村山聖と公園で出会うシーンがある。そのとき、森氏が村山聖の爪を点検し、「この人にほっぺたさわってもらい」というようなことを言うのだ。「この人」とは著者のことだが、ほっぺたをさわってもらいなさいという短い言葉のなかに、師匠と村山の愛情の深さが伝わってくる。村山聖の私生活は、師匠に爪を点検してもらうことが必要なほどいびつだった。しかし、著者は村山聖と師匠の森のやりとりのなかに、師匠と弟子以上の人間の交流を見い出す。
村山聖には、病気のなかで生死を見つめてきたがために、生きとし生けるものへの愛情深さがあったと描かれている。部屋のダニでさえ、殺さずに生かしておきたいという気持ちがありながら、それと相反する勝負の世界でシビアに戦いつづけた。相手棋士の道を封じる一手を磨きつづけた。そして29歳で、自らも実り多き今生の第一幕を終えた。